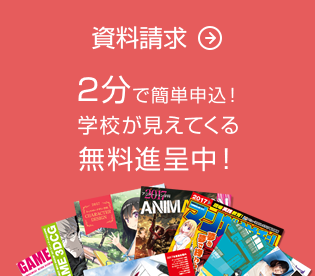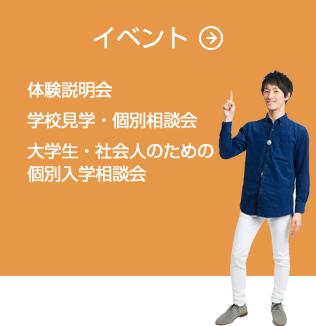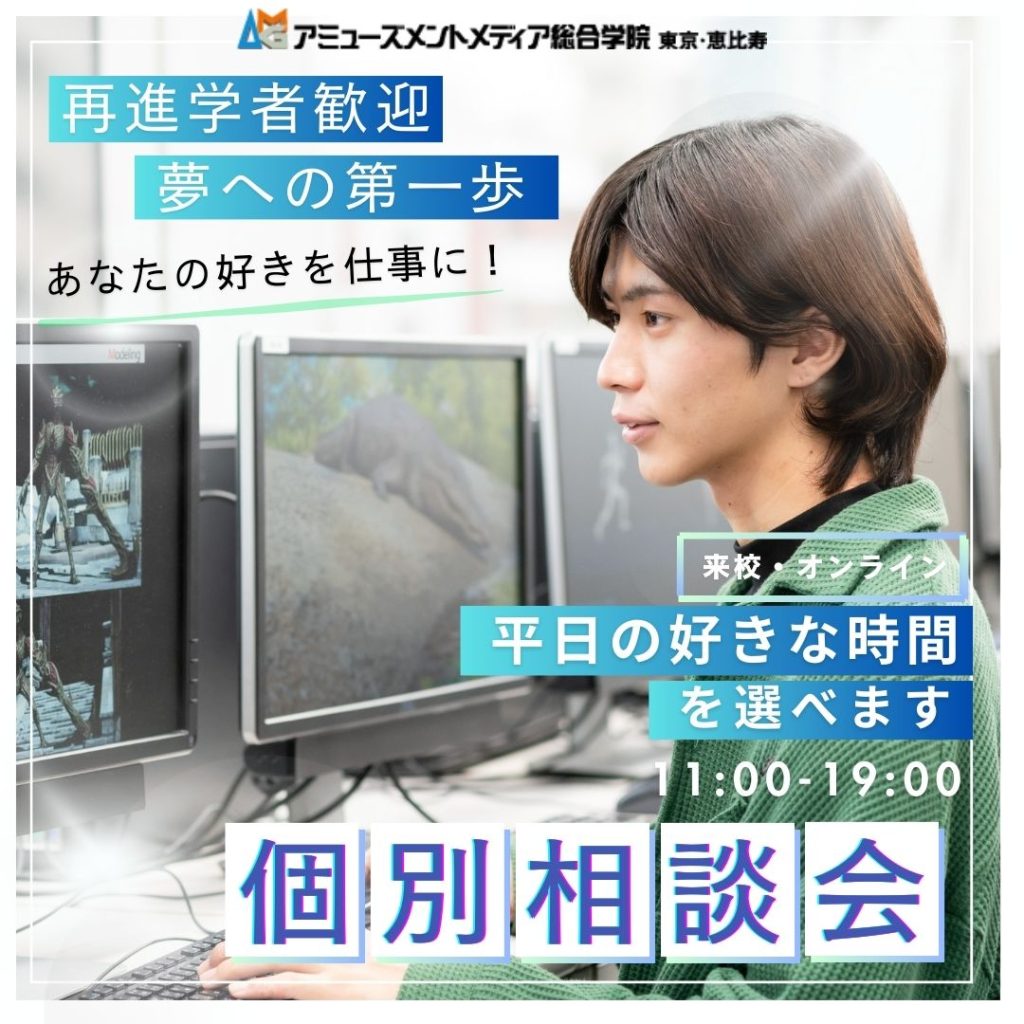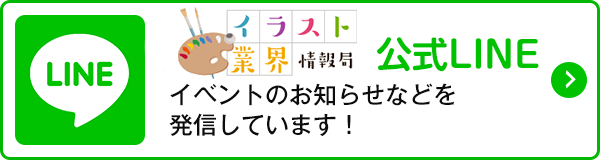「もっと絵が上手くなりたいけど、どんな練習をしたらいいかわからない…」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
イラストのスキルを上達させるには、練習を続けることが大事ですが、ただ何も考えずに自己流でやっていても上手くなりません。
この記事では、初心者向けの練習方法やコツといった、絵が上手くなる方法をご紹介していきます。
簡単に絵が上手くなる方法はありませんが、効率の良い練習方法は存在します。
初心者が行うべき練習方法について解説しますので、毎日少しずつ描き続けていきましょう。
目次
絵が上手くなる練習方法①トレース
トレースとは、お手本となるイラストの上にトレース用の紙を重ね、その上からお手本をなぞって描くことです。
イラストの基本的な描き方や上手な線の引き方などが学べるので、初心者におすすめできます。
練習するときは、ただ線をなぞるのではなく、イラストに使われているテクニックをよく見ながらなぞると効果的ですよ。
トレースの練習方法(アナログの場合)
アナログの場合、トレーシングペーパーをお手本のイラストの上に重ねて置き、鉛筆などでイラストをなぞっていきます。
トレーシングペーパーは半透明の薄い紙で、100円ショップなどでも購入できます。
また、トレース台を使用する場合は、以下の手順でトレースが可能です。
- お手本のイラストをトレース台に載せる
- その上にコピー用紙などを重ねて固定する
- トレース台のライトをつけるとイラストが透けて見えるので、鉛筆などでなぞる
トレース台があればトレーシングペーパーは必要ありません。
コピー用紙などに描けるため、色塗りも可能です。
トレースの練習方法(デジタルの場合)
デジタルの場合、ペイントソフトのレイヤー機能を使ってトレースができます。
- ペイントソフトでお手本となるイラストを開く
- お手本イラストの不透明度を20%~50%に下げる
- お手本イラストの上に、新しいレイヤーを作成してお手本をなぞる
トレースの練習での注意点
・トレースの練習だけでは絵は上手くならない
初心者がトレースをすることできれいな線の引き方を学べますが、トレースだけで絵が上達するわけではありません。
これからご紹介する他の練習も合わせて行ってくださいね。
・トレースしたイラストには著作権がある
トレースはコピーや複製と同じ扱いになるので、トレースしたイラストを公開する、配布するといった行為は、著作権の侵害になります。
また、お手本イラストを一部だけトレースしたものでも、著作権を侵害する可能性があるので注意してください。
絵が上手くなる練習方法②模写
模写とは、お手本のイラストをよく観察しながら描き写すことです。
お手本のイラストをなぞるトレースとは異なり、お手本のイラストを見ながら自分の力で絵を描きます。
トレースと比べてお手本のイラストそっくりに描くことが難しいので、観察力や絵全体、パースごとのバランス把握能力を磨くことが可能です。
模写するときも、ただなんとなく絵を書き写すのではなく、絵全体のバランスや描き方のテクニックなどをよく観察しましょう。
模写がおすすめな理由
模写の練習には様々なメリットがあるので、ご紹介します。
観察力が上がる
お手本イラストそっくりに模写をするには、線の描き方やパーツの位置、全体のバランスをよく見ながら丁寧に描く必要があります。
模写を繰り返すことで、観察力を身につけることが可能です。
モチベーションが上がる
自分の好きな作品やキャラクター、目標とする作家の絵を模写のお手本にすることで、楽しく練習することができます。
様々なイラストの模写を繰り返すことで上達していくので、モチベーションを保ちながら練習できるのは大事なことですね。
効率よくスキルアップできる
プロの絵を分析しながら模写をすることで、プロの技術を吸収することができます。
自己流で絵の練習をするよりも、模写を続けた方がはるかに効率よく絵を上達させることができるので、おすすめです。
上手に模写をするためのポイント
模写のスキルを上げるためのポイントを解説していきます。
絵の全体像を把握する
まずは絵全体のバランスを見ることが大事です。
イラストやマンガの一部だけを最初から丁寧に描き込むのではなく、まずは全体像を簡単な線で書いていきます。これがアウトライン(全体像)です。
「最初は全体、細かい部分は最後に」という順序を覚えておきましょう。
線を意識する
絵を模写する際は、線の強弱を意識しましょう。
プロの絵をよく見ると、太い線や細い線、勢いよく描かれた線、ぐにゃぐにゃしている線など、1つの絵の中に様々な線が描かれているのがわかります。
プロの描く線には必ず意図があり、「やわらかい物体を表現したいときはやわらかい線を使う」といった技術が使われているのです。
これは細部まで見ないと気がつかないかもしれません。
プロの線の引き方もよく観察しながら、模写をしてみてくださいね。
重心を意識する
人間の絵にリアリティが出ないのであれば、人物の重心を考えて模写をしてみましょう。
立っているポーズの場合、右足と左足のどちらに重心がかかっているのかを意識してみてください。
実際に自分が同じポーズをとってみることで、重心がどこに置かれて、どこの力が抜けているのかを理解できます。
ネガとポジから多角的に形を見る
「ネガ」とはネガティブの略で、「ポジ」とはポジティブの略です。
これらを絵で使う場合は、画面に占めるシルエットの外側がネガ、内側がポジとなります。
簡単に説明すると、絵を描いたときキャラクターのシルエットを切り取った際のシルエットがポジとなり、反対に残りの空白部分がネガです。
キャラクターだけを描くということよりも、キャラクター以外の部分も含めて全体のバランスを確認し、ネガとポジから多角的に形を見ましょう。
どうしてもメインとなるポジに目がいきやすくなりますが、ネガの形を面白くすることで、絵の構造を捉える力が上がり、絵の上達につながります。
質感を表現する
絵における質感とは、対象物に光をあてた際に現れる「光と影の領域」までの距離をいいます。
一番明るい部分から一番暗い影の部分までを表すことで、絵に質感が生まれるのです。
光と対象物の距離が遠いほど布のようなマットな質感となり、反対に近ければ近いほど金属のような反射率の高い質感が生まれます。
また、対象物が布の場合は、明度や色を緩やかに変化させ、なめらかに描くように意識すれば布の質感を表現できます。
さらにシワにも光と影をつけることで、より立体的に表現できるので試してみてください。
絵が上手くなる練習方法③人体構造の理解
人間を描く上で欠かせないのが、人体の構造を理解することです。
おおよその人体構造がわかっていないと、ポーズや動きの表現が不自然になってしまいます。
人間を描くときのポイントは「骨、関節、筋肉」です。
骨の構造を理解していると、体の各パーツの長さや大きさの比率が正しい絵が描けるようになります。
関節の構造を理解していれば、関節が曲がりすぎてしまう、手足の方向が不自然になるといったことが起こりにくくなります。
さらに筋肉のつき方を理解すれば、自然でリアルなボディラインを描くことが可能です。
人体構造を理解するための方法
人体構造は、実物やお手本を見ながら何度も描くことで理解することができます。
人体構造を理解するための練習方法をいくつかご紹介するので、参考にしてください。
クロッキーを行う
クロッキーとは、数秒〜10分ほどの時間で素早く人物や動物などを描写することです。
速写とも呼ばれ、瞬間的にモデルの特徴を捉えて、大事な要素だけをシンプルな線で伝える練習になります。
物体の構造の本質を最短距離で理解できるので、効率的に画力を上げられる練習方法です。
家族や知人、人物写真などをモデルにクロッキーを続けることで、頭身や骨格といった人体構造を理解できるようになるでしょう。
デッサンを行う
クロッキーの他に、デッサンも人体構造の理解に役立ちます。
デッサンはクロッキーよりも時間をかけて行い、対象物をよく観察して形や質感を捉えましょう。
人物モデルを観察して行うのが一般的ですが、デッサン人形でも代用が可能です。
デッサン人形はさまざまなポーズが取れるようになっています。
宙に浮いた状態のポーズや複雑なアクションシーンのポーズを作って、それを参考に絵を描くことも難しくありません。
デッサン人形は100円ショップで購入できるものもあれば、数万円する本格的なものまで幅広く販売されているので、予算や用途に合ったデッサン人形を持っておくことをおすすめします。
本を使って人体構造を学ぶ
美術用の人体構造の解説本を参考にするのもいいでしょう。
実物を見て描くことも大事ですが、美術用の本であれば「人間らしく描くにはどうしたらいいのか」といった絵を描くときのポイントも解説されています。
本を参考にする際は、必ず絵を描く人向けの解剖図が載っているものを選んでみてください。
アプリを使って人体構造を学ぶ
デッサン人形もおすすめですが、関節の調整をして自分でポーズの設定を決めようとすると時間がかかってしまいますよね。
そこで便利なのが、デッサン人形アプリです。
複数のポーズがプリセットされているアプリもあり、タップするだけであなたが練習したいポーズが描けます。
アプリを選ぶ際は、豊富なポーズ素材が入っているものにしましょう。
絵が上手くなる練習方法④顔のりんかくを描くコツ
りんかくが上手く描けないと、全体のバランスが悪くなります。
ここでは、顔のりんかくを上手に描くコツを紹介します。
アタリをとる方法
アタリとは下書き前のキャラクターの大きさや画面配置など、構成を決めるのに必要な円や楕円形のことです。
アタリを取ることで完成時のイメージがしやすくなります。
常にアタリを取るクセをつければ、安定したキャラクターを描けるようになるでしょう。
楕円を描く
卵型の楕円を描くのが理想的です。
まずは、アナログで楕円形を描く方法を紹介します。
- 長方形を4分割にする
- 1/4ごとに線を描いて楕円形にする
次に、デジタルの楕円ツールを使った方法です。
- 楕円ツールの中心を左上の角に合わせる
- 楕円ツールの終わりを対角線までドラッグ
楕円ツールで楕円を描き、その上から直接ペンで描き直すのもおすすめです。
また、楕円形を描くのは難しく乱れやすいので、慣れてきても左右反転を繰り返して練習しましょう。
正中線を描く
目の位置や大きさが左右対称になるよう顔に正中線を描きます。
しかし、横線が顔の中央にくると鼻の位置が高いため、正中線を描いた後、少し低めの位置に修正しましょう。
女性のほうが男性よりも低いイメージです。
ホホとアゴを描く
女性のホホは丸みを持たせ、男性のホホは直線的に描くのがポイントです。
頭からこめかみ、ホホまでは斜め内側に線を入れます。
さらにホホの丸みの位置は、正中線とアゴの真ん中にくると上手く描けます。
絵が上手くなる練習方法⑤髪の毛を描くコツ
髪の毛を描くときに「なんとなくボリュームがない」「顔と髪の向きがあっていない」など感じる方も多いでしょう。
顔が上手く描けても、髪の毛がしっかり描けないとバランスが悪くなってしまいます。
ここで髪の毛を描くコツを紹介します。
坊主頭にかつらを被せるイメージで描く
頭部の形がいまいち決まらないと感じている方は、一度キャラクターを坊主頭にしてみてください。
髪の毛の描き方は以下のようなものがあります。
- キャラクターを坊主にする
- 髪型のアタリを取る
- かつらを被せる
髪の毛を描く際は、頭蓋骨の形と生え際を意識してみてください。
髪の毛の生え際と流れを決める
生え際や流れを決めることで、より立体感のある髪の毛になります。
方法は以下の通りです。
- キャラクターを坊主頭にする
- 6つの生え際を決める
- 髪の毛の流れを決める
まず、生え際を作る場合は、「フロント・中央・サイド・もみあげ・バック・襟足」に分けるのがおすすめです。
それぞれわかりやすいように線で分けましょう。
そこから分け目に沿って、髪の毛が流れているようなイメージで描くと描きやすくなります。
また、つむじを中心に、放射状に生えているようなイメージにすれば、違和感のない髪の毛に見えるでしょう。
髪の毛で個性を演出できる
髪の毛を内巻きにしたり外はねしたりすることだけでも、個性を演出できます。
ここでは髪の毛によって個性が出るヘアスタイルを紹介します。
ショート
ショートヘアはキャラクターの個性を出しやすい髪型です。
・内巻き
内側にくるっとなった髪型は、ショートカットの中でもおとなしい印象となり、女の子らしさが出ます。
さらに少し後毛などもプラスして、ふわっと軽くすることで「かわいい」というイメージを与えられるでしょう。
・ボーイッシュ
ショートカットはボーイッシュさを出すのにも便利な髪型です。
触覚のようにクセをつけて、より個性を際立たせることもできます。
しかし、ショートカットを描くとき、髪の毛のはね具合でボサボサに見えてしまうので注意が必要です。
つむじと全体のバランスを取りながら描くことで、ボサボサの髪型になるのを防げます。
ミディアム
ミディアムは比較的フェミニンな印象を与えやすい髪型です。
・ストレート
肩に触れるくらいの長さにすればその部分が内側に入り、かわいさを演出できます。
反対に、外側にはねさせれば健康的な印象を与えられます。
キャラクターによって描き分けてみてください。
・ウェーブ
ウェーブは髪の毛を立体的に見せられるかが大切です。
ウェーブは最初に紙テープをイメージして描き、徐々に先端を細く描くようにしましょう。
また、同じ動きを何本も描くと不自然になってしまうため、巻きが強い部分だったりおくれ毛を数本入れたりするなど、自然に見せてください。
ロング
ロングはいろいろなアレンジができるので、個性を強くしたいときにおすすめです。
・ポニーテール
ポニーテールは頭のラインを考えて描くようにします。
また、横を向いたときに生え際を描くことで、よりリアリティを出せるでしょう。
・ストレート
ミディアムと同じ描き方ですが、ロングはボリュームによって重たい印象を与えます。
軽めにしたい場合は、先端だけ少しウェーブをつけると良いでしょう。
また、髪の毛の先端をパツンとカットしているように見せることで、意志の強さを表現できます。
絵が上手くなる方法⑥中級者編
少し絵を描くのに慣れてきたら、もう少しレベルを上げましょう。
ここでは、中級者におすすめの上達方法を紹介します。
丁寧に描く
「たくさん投稿したいので早く絵を完成させたい」「新しい絵を描きたい」など考えてしまうと、どんどん雑になってしまいます。
線を引くのも丁寧に行うことで、最後の仕上がりが全く変わります。
絵を描くことに慣れてきた頃は、初心に戻ってきちんと描くようにしましょう。
絵のお題を決める
これまで練習してきたものを、本番として作家さんやモデル人形で模写を行うのがおすすめです。
さらにキャラクターがどのような属性なのかも設定しておくと、性格などが見えてきてより人々の心に刺さる絵になります。
中級者になればある程度、自由なお題を作ってみるのも良いでしょう。
また、絵のお題を決めるためにも、自分のレベルを把握しなくてはなりません。
苦手なところを徹底して描く
上手く描けないと、どうしても苦手意識が芽生えがちです。
誰でも苦手だと思うことはそれぞれありますが、毎日の積み重ねで練習することで苦手意識が消え自信につながります。
人に見せてアドバイスをもらう
人に見せられるレベルになってきたら、自分よりも絵が上手い人に見せるのがおすすめです。
客観的に絵を見てもらうことで、「どこを直せば良いのか」のアドバイスがもらえます。
「人に見てもらうための絵」ということを意識しながら描くことで、もっと上手になりたい気持ちが強くなるでしょう。
また、誰かに自分の絵を褒めてもらうことで「承認欲求」が満たされ、モチベーションのアップにもつながります。
ときには厳しいことを言ってくれるような人に自分の絵を見せてフィードバックをもらえば、「悔しい」気持ちや「褒められるように頑張りたい」という気持ちが出てきて、練習にも力が入るはず。
絵が上手くなりたいなら専門学校に通うのがおすすめ

これまで、絵が上手くなる方法についてご紹介してきました。
もし将来、絵を描くことを仕事にしたいと考えているのであれば、専門学校に通うことをおすすめします。
毎日練習することでイラストが上達するのは確かですが、独学では限界があるのが事実です。
専門学校では、現役プロの講師に教えてもらえるので、指摘も明確で自分の苦手な部分の克服もしやすくなります。
また、就職や独立のサポートも受けられるので、プロへの近道ともいえるでしょう。
アミューズメントメディア総合学院では、絵の基礎からしっかりと学ぶことができる上に、在学中にプロの制作現場を経験しながらプロの仕事ができます!
絵を仕事にしたいという想いがある人は、ぜひ資料請求やオープンキャンパスに気軽に参加してみてくださいね。
プロのイラストレーターを目指すならAMGで学びませんか?
アミューズメントメディア総合学院のキャラクターデザイン学科は、独自の『現場実践教育』と『産学共同システム』により、エンターテインメント業界の現場と同じ環境で即戦力となるプロの技術やノウハウをしっかりと学ぶことができます。カバーイラスト実績500冊突破、加藤アカツキさん、ここかなたさんをはじめ、イラストレーターとして活躍している先輩を数多く輩出しています。
「絵を描くことが好き」「キャラクターデザイナーになりたい」というあなたの思いや夢をとことん応援します。ご興味がある方は以下のリンクをご覧ください。
アミューズメントメディア総合学院 キャラクターデザイン学科(東京)
監修・運営者情報
| 監修・運営者 | アミューズメントメディア総合学院 キャラクターデザイン学科 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区東2-29-8 |
| お問い合わせ | 0120-41-4600 |
| 詳しくはこちら | https://www.amgakuin.co.jp/contents/chara/ |