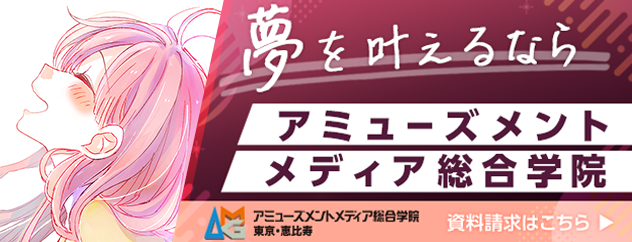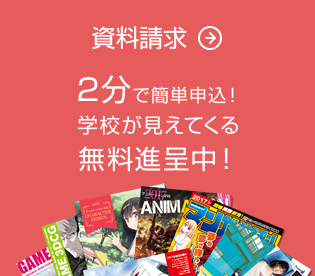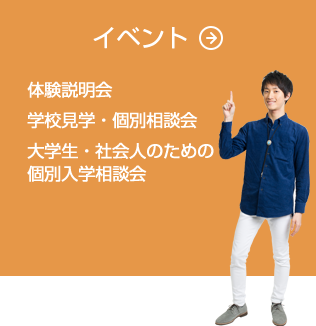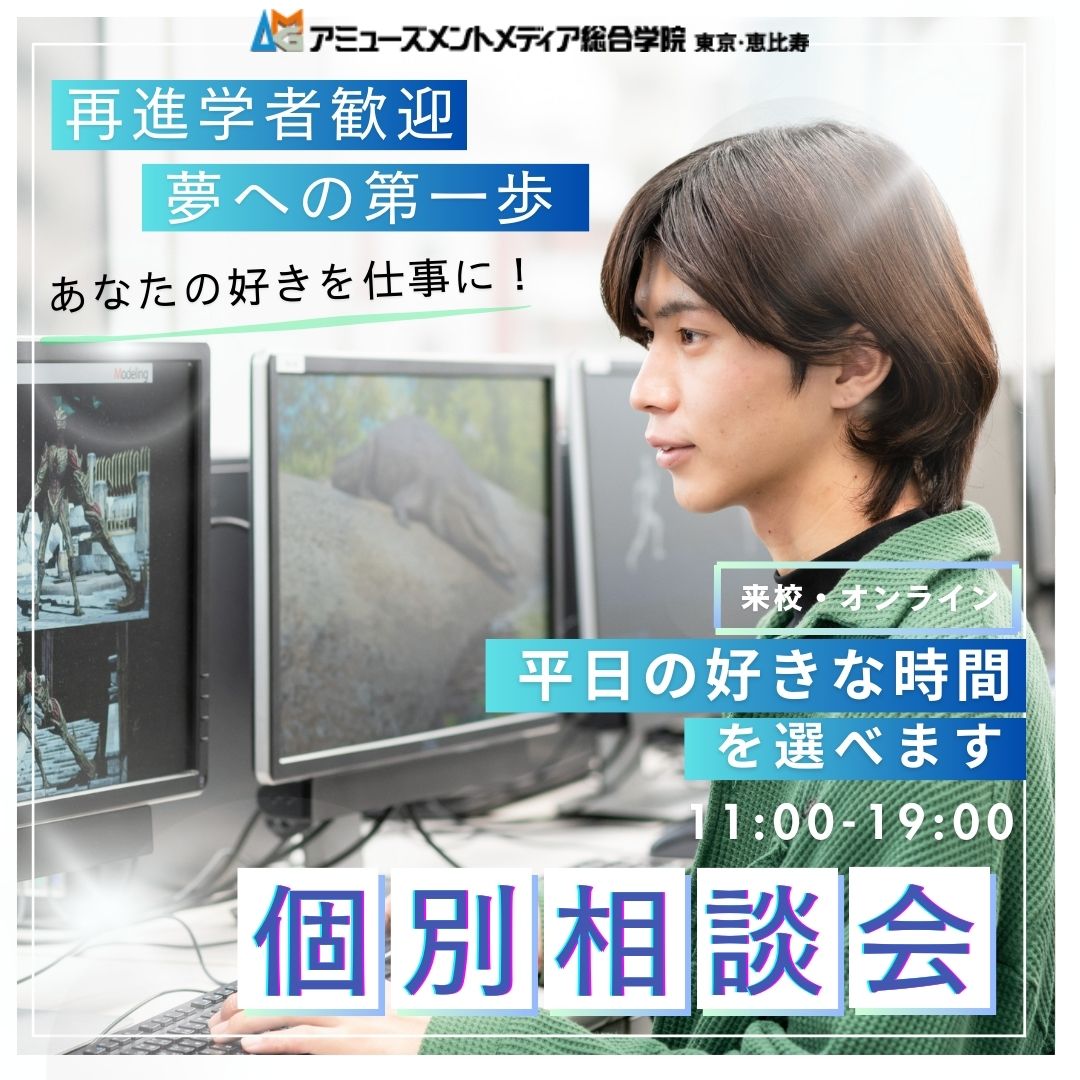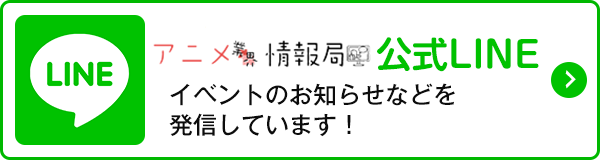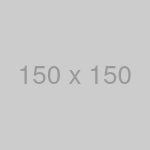
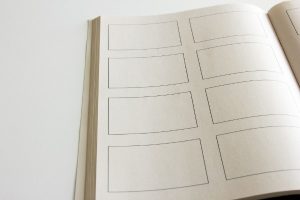 「中割り」はアニメ制作の専門用語の一つです。
「中割り」はアニメ制作の専門用語の一つです。
アニメ業界での就職を目指しているのなら、ぜひ知っておきたい用語になります。
中割りの出来は、見やすいアニメーションになるのかどうかの大きな肝です。
中割り担当者が手を抜いてしまうと、視聴者がアニメを見た時の印象が悪くなってしまう可能性もあるからです。
そこでここでは、アニメ制作における「中割り」について詳しく解説していきます。
参考にしてみてくださいね。
- この記事の監修者
- アミューズメントメディア総合学院は、東京恵比寿にあるゲーム、アニメ、マンガ、小説、声優などの 業界や職業を目指す方のための専門の学校です。アニメーション学科のurlはこちら。
- アニメーション学科では、動画/原画などを作るアニメーターやアニメ監督を目指すための「アニメーター・監督専攻コース」と、シナリオライターや、演出、制作プロデューサーを目指すための「制作・プロデューサー専攻コース」があります。講師は「機動戦士Zガンダム」で作画監督を担当する内田順久先生や、「マクロス7」で監督を務める網野哲郎先生など、現場で活躍している方が多くおり、生徒一人ひとりの成長を丁寧に指導しています。
- 体験説明会では実際にアニメをゼロから作ってみる講座などをやっていますので、ご興味がある人が是非参加してください!
- 体験説明会はこちら。
- この記事の監修者
- アミューズメントメディア総合学院は、東京恵比寿にあるゲーム、アニメ、マンガ、小説、声優などの 業界や職業を目指す方のための専門の学校です。アニメーション学科のurlはこちら。
- アニメーション学科では、動画/原画などを作るアニメーターやアニメ監督を目指すための「アニメーター・監督専攻コース」と、シナリオライターや、演出、制作プロデューサーを目指すための「制作・プロデューサー専攻コース」があります。講師は「機動戦士Zガンダム」で作画監督を担当する内田順久先生や、「マクロス7」で監督を務める網野哲郎先生など、現場で活躍している方が多くおり、生徒一人ひとりの成長を丁寧に指導しています。
- 体験説明会では実際にアニメをゼロから作ってみる講座などをやっていますので、ご興味がある人が是非参加してください!
- 体験説明会はこちら。
中割りとは
アニメーションにおける中割りとは、原画と原画の間の画のことです。
原画と原画の間の画を描くことで、実際にキャラクターなどが動いて見えるようにしています。
作画制作時の工程の一部で使われている用語です。
他に、中割りは作業自体を表す動詞として使われることもあります。
動画マンが作成する
中割りを作成するのは、「動画マン」と呼ばれている担当者です。
原画を動画のように動いて見せる為の画を描く人という捉え方がわかりやすいですね。
ちなみに、原画を描く担当者のことは「原画マン」と呼びます。
原画マンは、動画マンが描く中割りの枚数なども決める立場にあります。
その為、基本的には動画マンを経て原画マンへとキャリアアップしていくのが一般的です。
中割りの役割とは
さて、続いては中割りの役割について解説していきましょう。
主な役割は以下の2点です。
- キャラクターや背景の動きを滑らかにする
- 動きに臨場感を持たせる
これら2点において、更に詳しく見ていきます。
キャラクターや背景の動きを滑らかにする
中割りは、原画と原画の間の画なので、キャラクターたちの動きをより滑らかにすることが可能です。
例えば、歩いているシーンなのに右足を出す画と左足を出す画の2枚しかなかったら、キャラクターの動きはかなりカクカクしたものになってしまいますよね。
しかし、中割りがあればこのカクカクした動きをより滑らかに自然に見せることが可能になります。
アニメの世界であっても、3次元の世界と同じくらいに動きに違和感なく楽しみたいと思う視聴者がほとんどです。
この要望を叶える為にも、中割りは重要な役割を担っています。
動きに臨場感を持たせる

更に、中割りがあることでキャラクターなどの動きに臨場感を持たせることが可能になります。
例えばバトルシーンのパンチであれば、さようならと手を振るような動きで描いてしまうと、迫力がなくなりますよね。
そんな時、中割りの枚数を工夫すれば、パンチする前のポーズで少し動きをゆっくりにしつつ、最後には重みのあるパンチを敵にぶつける、といったことが出来るんです。
バトルシーンだけでなく、告白のシーンや喜びのシーン、その他キャラクターが感情を伝える場面で、より臨場感のある作画にすることが出来ます。
これは、中割りがあるからこそです。
中割りの主なテクニック
では、ここからは中割りの主なテクニックについて見ていきましょう。
よく使われるのは、以下の3つのテクニックです。
- タップ割り
- 線割り
- デッサン割り
それぞれの解説に移ります。
タップ割り
タップ割りとは、原画と原画の間の動きが大きいカットによく使われるテクニックです。
具体的な例としては、「手を振るようなシーン」などで使われます。
まずはクリップ等で原画と原画を重ね、上から中割りの位置を決めます。
手を振るカットであれば、左側にある手と右側にある手のどこかになります。
どこに中割りの位置を取るかは、後ほど紹介する「ツメ指示」によって決まります。
中割りの位置を決めたら、また原画を重ねて見てパーツの位置などがおかしくないか確認して、下書きを作成していきます。
動きの中でパーツの位置が不自然にならないようにしましょう。
ツメ指示について
ツメ指示とは、中割りの位置を指示するものです。
例えば、先ほど例に出した「手を振るシーン」であれば、重ねた原画と原画の真ん中に中割りを取るのか、やや左や右に寄った中割りを作成するのかの指示がわかります。
しかし、中にはツメ指示が書かれていない原画もあります。
この場合、まだ経験が浅いなら先輩に聞いてみるのが一番です。
中割りの作成に慣れてきたら、だんだんどこに中割りを取ればどのような動きになるのかが分かってくるので、ツメ指示がなくても大丈夫になります。
線割り
線割りは、原画と原画の間の動きがあまりない場合によく使われるテクニックです。
中割りの中では一番簡単なもので、大部分が重なった二つの原画の中間の線を引くように間の画を描いていきます。
その為、線割りは走りのシーンなどの一枚一枚動きが異なるカットでは使うことが出来ません。
デッサン割り

デッサン割りは、「振り向き」などの主に回転を使用するカットで使われるテクニックです。
振り向きは3次元的な動きになるので、タップ割りや線割りのような機械的な動きでは不自然になる部分を表現できます。
中割りのテクニックの中で最も難しいと言われています。
中割りの作成の流れ
では続いては、中割りの作成の流れを見ていきましょう。
簡単な流れとしては、以下になります。
- 動きのプランを立ててラフを作成
- 下書きの作成
- 作成した下書きをパラパラと動かし確認
- 清書して完成
それぞれの流れについて、より詳しく解説していきます。
1:動きのプランを立てラフを作成
まずは、中割りを作成する原画を受け取ります。
その際に、先ほど紹介した「タップ割り」「線割り」「デッサン割り」などテクニックのどれを使うのが良いのか決めます。
中割りを作成するプランを決めたら、今度は原画を重ねて中割りの位置を決め、簡単にラフを作成します。
ラフである程度イメージが固まったら、次は下書きに入っていきます。
2:下書きの作成
中割りの下書きは、ある程度の動きがわかるように描きます。
さらさらっと描いてしまうと、自分が清書する時に困ってしまうからです。
特に、キャラクターの腕や足の位置などは大切なので、しっかり描き込みましょう。
3:作成した下書きをパラパラと動かし確認
下書きが完成したら、原画と合わせてパラパラマンガのように手で動かして確認します。
この時に少しでも動きが不自然になっていると感じたら、下書きからやり直してまた確認を繰り返します。
例えば、走るシーンなどは頭の位置などが不自然になりやすいので、ちゃんと確認しておきましょう。
4:清書して完成
原画と合わせて確認して不自然でなければ、そのまま清書に移ります。
実際にアニメーションとして動く部分になるので、丁寧に描きましょう。
中割りが作画崩壊として勘違いされる理由
アニメが好きな方の中には、作画崩壊という言葉を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。
実は、この作画崩壊は中割りと勘違いされてしまっていることもあります。
中割りはあくまで動いているように画を描いていくことなので、一瞬の体の歪みなども表現しています。
しかし、この歪みを「作画崩壊」と勘違いしてしまう方もいるんですね。
これは、現在ではスマートフォンなどで簡単にアニメのキャプチャを撮ることが出来る為に、中割りの部分を撮ってしまうと作画崩壊のように見えるからです。
作画崩壊とは、基本的には原画の時点で画のクオリティが低い状態のことを指します。
例えば、背景パースが狂っていたり、止まっているシーンのキャラクターの顔が別人であったりなどです。
一方、中割りは動きを描いている部分なので、歪みなどがあることはおかしいことではありません。
全体のアニメーションとして違和感のないシーンであれば、中割りとしての役目は果たしていることになるので、作画崩壊ではありません。
勘違いしないようにしてくださいね。
まとめ
いかがでしたか。
ここでは、中割りについて詳しく解説してきました。
中割りがあることで、違和感のないアニメーションとして見ることが出来るということが分かったのではないでしょうか。
最後に中割りについて簡単に振り返ってみましょう。
- 中割りとは原画と原画の間の画、またはその制作作業自体のこと
- 中割りは動画マンと呼ばれる担当者が作成する
- 中割りがあることで、キャラクターなどの動きを滑らかにし、動きに臨場感を持たせられる
- 主に「タップ割り」「線割」「デッサン割」等のテクニックがある
アニメーションは、中割りのクオリティで違和感なく見られるかどうかが決まると言っても過言ではありません。
動画マンとして働いていく為には、今からデッサンなどで基礎的な画力を磨いていくのが一番です。
東京でアニメーション業界を目指されている方は「アミューズメントメディア総合学院」で学びませんか?
東京のアミューズメントメディア総合学院のアニメーション学科は、就職希望者内定率が7年連続100%を達成しています。「絵を仕事にしたい!」という方のためのアニメーター専攻と、「沢山の人に影響を与える作品を創りたい!」という方のためのアニメ監督・演出専攻があります。また第一線で活躍中のプロが直接指導。少人数制で講師と学生の距離が近いから、一人ひとりに合った指導を行うことができます。ご興味がある方は以下のリンクをご覧ください。
監修・運営者情報
| 監修・運営者 | アミューズメントメディア総合学院 アニメーション学科 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区東2-29-8 |
| お問い合わせ | 0120-41-4600 |
| 詳しくはこちら | https://www.amgakuin.co.jp/contents/animation/ |