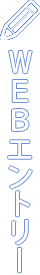――「ペインター(描画ソフト)を使ったからって寺田克也みたいに描ける訳じゃないんだ」っていったのは安彦良和さんでしたっけ?
それは……鈴木みそじゃないですかね(笑)
――ああ(笑)。安彦さんとは雑誌「ガンダムA」(角川書店)で対談されていますよね。あの中で、そんな話があったように思うんですけど。
ああ。おっしゃってたかも知れないですね。
――このところ、寺田さんはいろんな方と対談されていますよね。安彦さんの他に、大友(克洋)さんや空山(基)さんといった方々と。それは、寺田さんがリスペクトされてる方ってことなんでしょうか。
それは間違いないです。なんらかの影響を与えてもらってる人っていう。
――大友さんやほかの方とはじめてお会いになってみて、どうでしたか。
それはねえ、不思議な感じですよ。自分の感覚って、田舎で絵を描いてる時とあんま変わってないんですよ。だから「俺、なんでこの人と話してるんだろ」という感じは拭いがたいですよ。
――田舎にいたころの、仰ぎ見ていた感覚?
そうそう。遠い世界の人たちと一緒に話してる、っていう。……まあ、実際にお会いすると話も面白かったりするので、作品の面白い方は本人も面白いっていうことを確認している感じはしますね。そういう、自分の「におい」の感覚は間違ってないのかな、というあたりが実に嬉しいというか。
――とはいっても、寺田さん自身の立ち位置というか、見られ方は変わってきていますよね。いま、日本のキャラクターイラストの世界では、第一人者として見られている。
どう……なんですか。立ち位置はね、変わんないんですよ。ただ、変わらざるを得ない所はありますよね。「寺田克也」の名前で仕事していると、そういう状況の楽な部分と楽じゃない部分と、ってのは否が応にも考えなきゃいけない。
――ブランド感があるというか、過去の寺田さんの仕事を見たクライエントが「寺田克也だから大丈夫」と、先に評価してしまうとか。
それはもう、解ってたことですよね。そういう状況ってのはあるだろうと………十代の若者が、いきなり放り込まれると大変な事になるかもしれないんですけど、幸いな事にそうではない、という。わかりやすい話すると、自分の落描きが本になってしまうわけですよ。それは普通ではありえないことで。だから俺の落描きがいい、っていってんじゃなくて、本来企画として中々通らない筈なのが通ってしまうってことは、俺にとってはすごい危険なことなんですよね。下手すると、じゃあ落描きを出せばいいのかって、そっちに行きがちになってしまう。
――反面、やりやすいというか、自由になってきた部分もあるんじゃないですか。
いや、逆にいうと自由ではなくて。「寺田克也」というイメージがすでにあって、それに捕われるってことでは、より不自由になってるわけだから。やりたいことやれてるように見えて、その反面凄く窮屈にはなっていくですよね。それ以上、それ以外はさせない、ってことでもあるわけだから。

――そこを何とか、上手くこう広げていこう、という作業は……?
するんですけど、それはその、絵を描く作業とはまた別の話になってくるんですよね。
――いってみれば「自分内プロデューサー」みたいな。
そうそう。プロの職人として看板挙げている以上は、そういうプロデュースする能力は絶対必要ですよね。
――これはどんな表現のジャンルでもそうだと思うんですが、受け手ってひどく貪欲なところがあるじゃないですか。常に「もっと、もっと新しいものを見せて」っていう要求があって。
ありますね。それは自分の中にもありますよ。
――だから、落描きでも商品になるんですが、一方で「新しいものを」となった場合、描き手のなかでの要求ってのはもっと凶悪だと思うんですよ。こっちは質的にもっと高みを…っていう方へ行っちゃうから。
本人は変わろうとしますからね。
――プロになる前の寺田さんというのは、もう黙ってても、とにかく描いてたっていう感じだったんですか。
まあ、それはね(笑)。イメージ的にはそうなだけなんですけど、はっきりいって何もしてなかったですよ(笑)。学校のとき、阿佐美(阿佐ヶ谷美術専門学校)にいたときは、そんなに描いてないです。描いてないっていういい方をするとまたちょっと違うんだけど……いわゆる、ちゃんとした絵は一枚も描いてないに等しいですよ。落描きばっかりしてて。
――落描きは、「止めろ」といわれても描いちゃうくらい?
いや、それもねえ……わりとイメージで語っててねえ。
――そうなんですか?
いうほどやってないっすよ。ただ、「見る訓練」はしてたような気がします。じゃあ、どんな訓練なんだっていわれると、答えに詰まるんですけど。んー。雰囲気をつかむっていうか、そういうのがありましたね。
中学、高校のころからですね、何かの絵を描きたいと思った時に、描けない。たとえばバイクを描こうとしたらバイクが描けない。バイクの資料を集めてこなきゃいけないわけですけど、お金もないですからね。カメラもないし、コンピュータもない。写真を撮ろうにも、町にそうそうバイク走ってない。そういうことが色々あったので、どうすれば一番、楽だろうと考えたわけです、子供心にね。それで、何にも見ないで何でも描けることが一番楽だなと思ったわけですよ。そこで、ふだんから見てるものを、全部、そのニュアンスで覚えておこうという感覚を、その頃から強く持つようになったんですよ。
――ニュアンスで覚える。
そう。たとえば、ここに砂糖入れがありますよね。これを覚えちゃうんです。丸暗記っていうのとは違うんですけど。
砂糖入れが何で出来ているのか、どう開くのか、とか。どう開くのかにしても、正確にわかんなくても、「開きそうだな」と思えればいいわけですよ。開きそうだなと思うためには、フタのここに蝶番がないといけないとかね、そういうのはわかるから、それを頭に入れていくっていう作業を、わりと自然にしてたんですよ。
これは「記憶力」とはまた全然別の話で。じゃあ正確に描けって言われると信号どっちが赤だっけ、みたいな話なんですよ。ただ信号が三つ、ライトが三つっていうのはもうわかってて、大体の形もわかってて、上に覆いがこう被ってる。その覆いであるとか、それがどういう風に留められているとか。そういうのを見るようにしてたんですよ。
そういう作業ってのは、結局、絵を描くのと一緒なんですよね。絵を描くときにどうするかっていうと、こう(対象を)見るわけですよね。こう見てこう見てこう見て、紙の上に形をとっていく、それを頭の中でやっているっていうのがありました。そういうことが、知らず知らずのうちに訓練にはなってたんじゃないかと。
――子供のころの絵も、本(「ペインタボン」ラピュータ 2002)に載せてらっしゃいますけど、子供のころから主に描いてたものっていうと……
主に描いてたものはないですよ。
――ないですか。なんでも描いてた?
いや、ろくなものは描いてないですよ。マンガのキャラクターであるとか。そういったものですよ。描きたいものもないんですよね。それはいまだにそうなんですけど。だから、絵で「いいたいこと」はないんですよ、別に。「いいたいこと」はクライアントが持ってくるんですね。
――こういう設定でこう……とか。
そう。それをどう見せるのか、っていうことなんですね。俺は、あくまで「見せ方」を求めてる人ですから。「いいたいこと」とかは仕事頼む人が持って来るものだし、見る人が考えることだし。そこらへんはね、考えない、俺は。
――とくに「これが描きたい」っていう対象はないんですか。
それは、昔からないです。というよりも、むしろ、何か描いて、人に見せると喜ばれる、っていうのがワンセットになってますから。
――サービス精神みたいな。
そう、根がそうなんですよね。最近よく「サービス業だな」っていってるんですよ。「サービス」っていうのは、すごく乱暴に言えばコストを度外視することかなって思うんですよね。全てのサービスがね。その、だから、自分が仕事をいただいたときに、どこのコストを度外視しようかっていう話になってくるわけです。俺の場合、求められてるからには、なるべく見たこと無いもの出したいっていうのが強くありますね。それが、いま自分が仕事をしているフィールドともうまく合ってると想うんですよ。
たとえば、車の絵とかを描いていれば、車は元々あるもんですから、また別の働きになっていくんですけど、いわゆるファンタジーものとか、そういうものなわけでしょう。その存在意義を考えると、ホントはないものを描いているわけだから、とにかく人の想像を超えるものを描くしか売りがないわけですよね。そこにはやっぱり腐心するべきだと思うんですよね。だから、ちょうどフィールドが合ってたっていうのはありますけどね。こういうことは、「キャラクターデザイン」という仕事全体の話になってくるんじゃないかと思うんですけどね。

――キャラクターっていうもの自体が、現実には存在しないものなわけですし。
「いないもの」っていうか、何かを背負わせるものですから。
――背負わせるってのは、概念とか?
その、背負わせたものが、重くない形にしないといけないわけですよね。
――重く感じさせない、というと?
目的によると思うんですけどね。自分の価値観のひとつに「さりげない」っていうのがあるんですけど、そこらへんに端を発する感覚かもしれないんですけどね。たとえば『BLOOD』のキャラクターデザインをしたとき、いただいた設定ていうのが、セーラー服を着て女子高生で日本刀もってる、しかもアニメであるっていうものだったんです。それで、資料についてきた(キャラのイメージを示す)ちっちゃい絵が、わりと長髪のすらっとした女の子で。ところが、それを描いてしまうと、どっかで見たことがあるようなものにしかなりえない。それが、俺にいわせると「重い」わけなんですよね。イメージを背負わせすぎてるっていうかね。
そこを外しながら、なおかつ外しきらないラインってのはなんだろうって考えるわけですよ。そうするとお下げになったりするんですね。ちょっとなるべくブス寸前で唇厚くするとか。そういう作業が差別化になっていくんですけど、そこはまあ、なかなか曰く説明しがたい。センスの問題かもしれないんですけど。
――背負わせすぎてる、というところをもう少し伺いたいなと思うんですけど。
背負わせすぎてる、っていうのは、やっぱり人はイメージの生き物なのでね。概念としても生きてしまう。観念でね、生きてしまう。アニメ・セーラー服・日本刀って聞いたときに「長髪」っていうのはものすごい俺の中ではもう観念としてあったわけ。
――セーラー服のもっている意味とか、日本刀の持っている意味とか……。
絵的にね、見たことあるんじゃねえかな、っていう気がしてくるわけ。それは俺の感覚だけなのかもしれないんですけど、その時に感じたのは、もう俺が感じちゃったんでしょうがないんで、ココは絶対外さないといけないな、と。
――過去に語られたり、描かれたりしたものが背負っていた物語であるとか、意味とかを引っ張ってきちゃう、てことですか?
ようするに見たことあるものはつまんないでしょ? で、見たことないものを提供したいっていう部分を追求していくと、長髪……はないでしょう、ってなるという話だけなんですよ。これはもう説明じゃないんですよね。感覚だから。自分も、そこで嬉々として長髪で可愛い子を描いてしまうかもしれないし、それで見たこともないものが生まれたら、もっとすごいと思うんですけど、俺はそういう自信がなかったんですよ。そこで、寺田克也が頼まれて出すものって、やっぱり長髪じゃないよね、って自分のなかのプロデューサーが叫ぶわけですよね。
――自分内プロデューサーの側が?
「見たことないものを見せてくれ」っていうのは大前提だから。ここで見たことあるものはもう出せないし。そのラフについてきた絵でもう既に見ているわけだから、なおかつね。いってみればさ。
――説明がついてる。
そうそう。そうするとそのまんま、まんまで来るのかよこいつ、っていう話になって来るでしょ。ここで打ち返す時に、じゃあ何を打ち返すかっていう話にもなってくるし。それは仕事の駆け引きの面でもあるわけだけど、それ以上にさっきいったサービス、自分に対してのサービスだし、クライアントに対してのサービスだし、見てる人に対してのサービスで、そこの落としどころを見つけるっていう作業になってるわけですよ。
―それが毎度のことなわけですよね。
そうそう、毎度毎度。
――プロデューサーじゃない側もいるわけではないですか、自分の中に。
いや、それはプロデューサーに隷属するもんですよ。それ以外ありえないと思いますよ。で、もし俺がね、もうホントに、長髪の女の子しか描けないし、長髪大好きでたまんないっていう人間であれば、長髪で出してくるし、頼む側もその長髪を求めて頼んでくるはずだから、それはそのまま出しますけど。そうではないのはもう知ってるわけだから。そこで長髪は描けないわけですよね。そのへんはもう瞬時に考えちゃうことだから、説明すると何をご大層なって話になってくるんですけど。
――一方で、本当に内的な部分で、より自分にとって良い絵を描いていこうっていうのがあると思うんですよ。より自分にとっての高みを目指す欲望というか。
それはねえ、自分の手が自分のなかの基準に追いつくことはありえないんですよ。それは絶対、いっつもそうなんですね、最初からそう。自分にはこれしか描けないのか、っていうレベルのことを延々やっているわけだから。それは昔から変わりませんね。
――これからも変わらないですか。
変わらないでしょうねー。変わったとしたら、もうそこで絵を描くのは終わるんじゃないですかねー。そういうことが起こるかどうかわかんないですからね。
――「気が済んじゃう」みたいな感じのことが。
気が済む、ってことは多分ないってことだから。追いつくことはありえないわけですよね。ただその、明らかにスピードってのは落ちていくんですよね。体力的なこともあるし。ここからここまでの表現を手に入れると、その先ってのはどんどんタイトになっていくんですよ。そういうタイトさはもうずっとあって、「こんだけしか描けないのかな」っていうのは常にあるわけですよ。そこのせめぎあいは常にあるんだけど、それはすごく普通のことなので、取り立てて深刻に思わないようにしてます。
――それはもう、あるものとして。
そうそう。あるものですよね。あるものだとし、あるものということを教わっているような気がしますよね。いろんな事からね。
――「あるんだからしょうがない」みたいな。
そうそうそう。俺は基本的にはそういう感覚でいたいので。
――たとえば「飯食わなきゃ腹減るよ」みたいな、あたりまえの感覚に近いとか?
とりあえず食えばまあなんとか生きていける、みたいな。だからね、悩むところと悩まないところって、明快にしとかないといけないっていうのが常にあるんですよね。
<聞き手:伊藤剛>
[PROFILE]
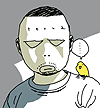
寺田 克也
日本を代表するグラフィックアーティスト。美術専門学校在学中からイラストの仕事を始め、卒業後はフリーのイラストレーター、漫画家に。イラスト、漫画をはじめ、ゲーム、映画など様々な分野で活躍。ゲーム『バーチャファイター2』『カリーンの 剣』ほか、2000年度文化庁メディア芸術祭アニメーション部門大賞を受賞した『BLOOD THE LAST VAMPIRE』では、映画・ゲームのキャラクターデザイン、小説の想定までを手掛けた。近作では、窪塚洋介、佐藤浩市主演の話題作、映画『魔界転生』のイラストレーションも手掛けた。『新世紀エヴァンゲリオン』の庵野秀明監督の劇場最新作として発表された『キューティーハニー』では、キャラクターデザインを担当している。